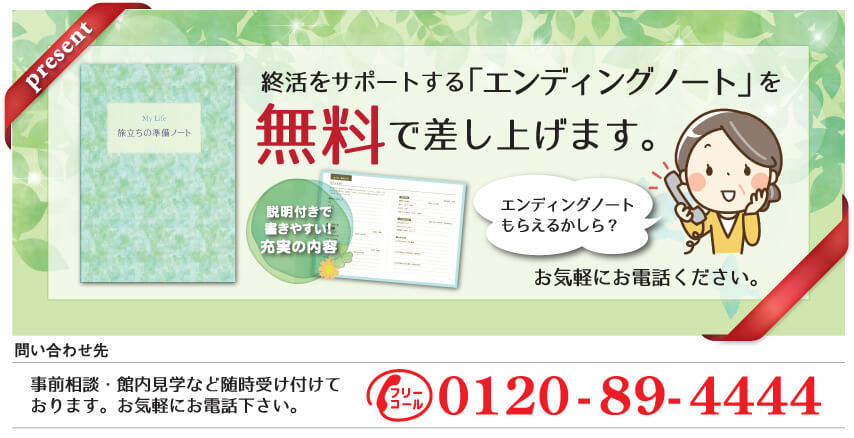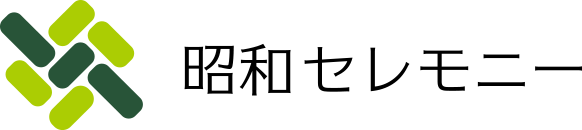施主と喪主の違いと役割とは?葬儀マナーをご紹介

昨今の葬儀では、施主と喪主を同じ人が担当するケースがありますが、厳密にいえばこの2つは似て非なるものです。
今回は施主と喪主、それぞれの役割と知っておくべき葬儀マナーについて解説いたします。
今回は施主と喪主、それぞれの役割と知っておくべき葬儀マナーについて解説いたします。
主は葬儀の金銭面をまとめる役割
基本的に施主を務める人は血縁関係に左右されず、当主がその役目を担います。施主の「施」はお布施を意味しており、その葬儀の金銭面を取りまとめる代表です。
お布施は直接渡すのではなく、お盆や菓子折りに乗せるのが一般的です。包む際は、奉書紙と白の封筒の2つの方法があります。水引は一般的に必要ないとされていますが、これも地域の慣習によって変わってきます。
地域ごとの慣習によって、お布施を僧侶に渡すタイミングも異なってきます。一般的には葬儀当日に渡すパターンが多いですが、状況によって用意できていない場合は葬儀社に聞いてみましょう。
お布施は直接渡すのではなく、お盆や菓子折りに乗せるのが一般的です。包む際は、奉書紙と白の封筒の2つの方法があります。水引は一般的に必要ないとされていますが、これも地域の慣習によって変わってきます。
地域ごとの慣習によって、お布施を僧侶に渡すタイミングも異なってきます。一般的には葬儀当日に渡すパターンが多いですが、状況によって用意できていない場合は葬儀社に聞いてみましょう。
- 香典の扱いには注意
施主は香典の扱いに注意しましょう。香典は出棺の際に係から受け取るのが一般的ですが、このとき喪主は挨拶をしているため慌ただしくしています。そのため、施主が代わりに受け取って大切に管理するとスムーズに葬儀が進んでいきます。
喪主は葬儀全体を取りまとめる役割
喪主は施主と異なり、血縁関係によって務める人を決めるケースが多く、故人とより近しい人が担います。故人が配偶者の場合は夫や妻が、配偶者がいない場合はその子どもです。施主が金銭面を取りまとめるのに対して、喪主は葬儀全体を取りまとめる代表であるため、葬儀社との打ち合わせや連絡の窓口、参列した方々への応対、出棺の際の挨拶といったことを主に行います。
重要な仕事が多く大変だと感じるかもしれませんが、喪主1人ですべて行う必要はなく、家族や兄弟姉妹と協力します。
重要な仕事が多く大変だと感じるかもしれませんが、喪主1人ですべて行う必要はなく、家族や兄弟姉妹と協力します。
喪主の重要な役目の1つである参列者への挨拶について

地域によって慣習の関係で通夜での挨拶は必要としない場合もありますが、葬儀では喪主が代表して必ず挨拶を行います。挨拶は特別工夫することは求められませんが、参列者が来てくれたこと、生前にお世話になったこと、今後変わらないお付き合いを願うこと、これらは最低限取り入れて伝えましょう。
故人に対する気持ちは十分にわかりますが、あまり湿っぽい挨拶では全体も暗くなってしまうので、見送る思いを忘れないでください。喪主が挨拶を行うタイミングは参列者に対して個別に行うもののほかに、葬儀終了後、精進落としの前後があります。
挨拶の内容はスムーズに進められるように覚えておくのがベストです。参列される方々と故人の関係性によって用意するとよいでしょう。たとえば、友人関係が多い場合は形式を守りつつ多少くだけた内容で人柄を語る、仕事関係が多い場合はあまり仕事上で差し障りないよう具体的な話は避ける、といったことをおすすめします。
故人に対する気持ちは十分にわかりますが、あまり湿っぽい挨拶では全体も暗くなってしまうので、見送る思いを忘れないでください。喪主が挨拶を行うタイミングは参列者に対して個別に行うもののほかに、葬儀終了後、精進落としの前後があります。
挨拶の内容はスムーズに進められるように覚えておくのがベストです。参列される方々と故人の関係性によって用意するとよいでしょう。たとえば、友人関係が多い場合は形式を守りつつ多少くだけた内容で人柄を語る、仕事関係が多い場合はあまり仕事上で差し障りないよう具体的な話は避ける、といったことをおすすめします。
まとめ
かつての日本では家督総督によって、家長が亡くなった場合はその長男のみが相続する権利を持っていました。そのため、喪主を担うのは相続する長男だとされてきましたが、年月とともにさまざまな変化もあり、現代では誰が務めるのか絶対的な決まりはありません。
施主と喪主を同じ人が務める場合もありますが、規模によっては非常に荷が重くなってしまうので、できることなら別々に担当することも検討してください。葬儀は故人を尊重するとともに、生前お世話になった人々に対して感謝を伝える重要な場なので、粗相のないようにしっかりと務められるようにしましょう。
施主と喪主を同じ人が務める場合もありますが、規模によっては非常に荷が重くなってしまうので、できることなら別々に担当することも検討してください。葬儀は故人を尊重するとともに、生前お世話になった人々に対して感謝を伝える重要な場なので、粗相のないようにしっかりと務められるようにしましょう。